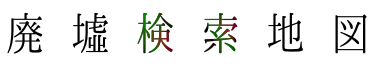ケーブルハットの検索結果
、小田原市谷津の畑の中にもあり、「バベルの塔」と通称されていたが、既に解体されている。またかつては横浜市内にもあったが撤去されているらしい。
2018年11月現在、豊川市野口町の施設跡には案内板が設置され管理されている。
なお、同じく長距離電話関連の遺構としてはケーブルハットが全国に残っている。
を通す際に建てられたという木製の電柱が多数、「〒」マークのついたコンクリート製の小屋が2箇所ある。「郵便小屋」は、電信装置に使われた「中継線輪」と言うコイルを収納していた小屋とも言われたが、長距離地下電話ケーブルの信号減衰を防ぐために50kmごとに設けられた逓信省装荷線輪装置用ケーブルハットらしい。
瀬戸新屋のケーブルハット。
逓信省装荷線輪装置用ケーブルハットとは、昭和初期に用いられた長距離市外電話用地下ケーブルの中継施設である。
藤枝市のケーブルハットは藤枝海軍航空基地の関連遺構と誤認されていたが、実際は通信関係の設備だった。
交差点のそばに大きな破損等もなく残っており、壁に看板が取り
御殿場市のケーブルハットらしき倉庫。富士山御殿場口や滝ヶ原駐屯地へ向かう滝ケ原街道(富士山スカイライン)沿いに位置する。
大きさは高さと横幅が約2m、奥行きが約1.5mほどで、劣化によるものなのか壁の剥離や地面との接地面の浮き上がりが目立ち、〒マーク等は見られない。
入口には小さな庇があり、その
苦の坂峠のケーブルハット。
逓信省装荷線輪装置用ケーブルハットとは、昭和初期に用いられた長距離市外電話用地下ケーブルの中継施設である。
1890(明治23)年に日本で電話が初めて敷設されて以来、主要都市間の電話網整備が進められ、1939(昭和14)年には東京から満洲国(当時)の哈爾浜(ハルピン)
残っている。戦後に米軍が弾薬を搬出したが途中で崩落したため、そのまま入り口を爆破閉塞させたが、後の宅地化開発に際して調査したところ爆弾が見つかり1989年不発弾処理されたという。
JR藤枝駅近くに弾薬庫跡らしい建物があるが、これは逓信省装荷線輪装置用ケーブルハットで、藤枝海軍航空基地とは関係ない。
た長距離市外電話用地下ケーブルの中継施設である。信号減衰を防ぐために50kmごとに設置されていた。
減衰を防ぐために50kmごとに設置されていた。
坂遂道西のケーブルハット。国道362号本坂トンネル旧道に位置する。
逓信省装荷線輪装置用ケーブルハットとは、昭和初期に用いられた長距離市外電話用地下ケーブルの中継施設である。信号の減衰を防ぐために50kmごとに設置されていた。
本坂遂道西のケーブルハットは朽ちた状態で長く残っていたが、2020年